- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
【中古】【茶器/茶道具 蓋置】 染竹蓋置 一双(炉用・風炉用)花押付 堀之内宗完付 影林宗篤作
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
残り 1 点 38491円
(10 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-





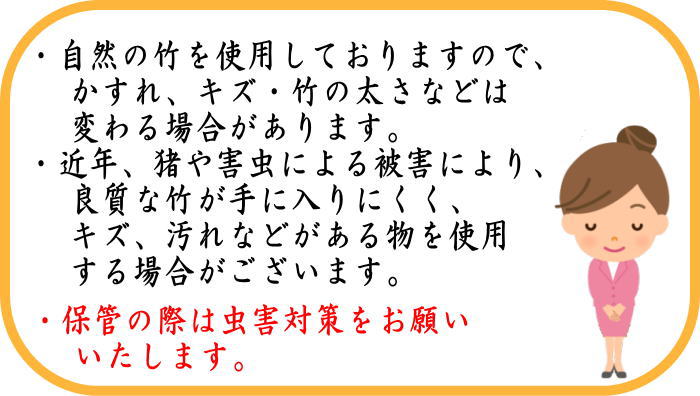























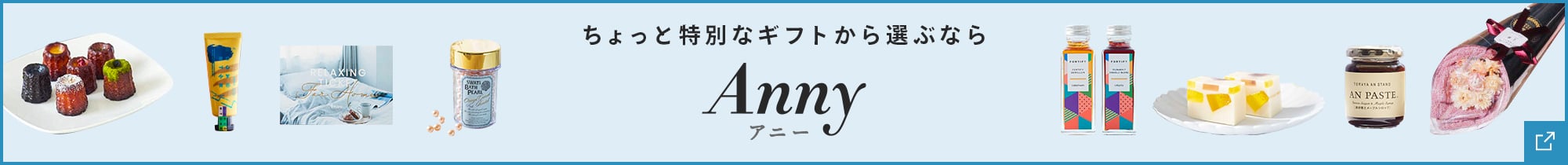




風炉用:直径5×高さ6.3cm
影林宗篤作
(堀内家は江戸中期の堀内仙鶴を祖としています。)
【初代 堀内仙鶴 化笛斎】
浄佐の養子で、はじめ水間沾徳の門で俳諧を学び、のちに江戸を去り表千家6代覚々斎の門下に入った。
【2代 宗心 不寂斎】
【3代 宗啄】
【4代 宗心 方合斎】
高槻藩の出身であったため、以後高槻藩永井家の茶頭を務めた。
【5代 宗完 不識斎】
【6代 宗瑛 如是斎】
【7代 宗晋 至慎斎】
【8代 松翁宗完 不寂斎】
明治8年(1875年)にタワフル夕顔蒔絵の立礼卓を考案し、表千家に立礼式を受容した。(タワフル立礼棚)
【9代 宗完 的斎】
【11代 宗完 幽峯斎】
【12代 宗完 兼中斎】
京都帝国大学理学部の出身で独特の茶風で知られる
1919- 昭和後期-平成時代の茶道家【表千家流堀内家 12代 宗完(斎号(兼中斎)・隠居後(宗心))】
1919年大正08年1月20日生まれ(名は吉彦)堀内家の庵号(長生庵主)
兄の11代が急逝したため,表千家13代千宗左に師事
1953年昭和28年 宗完を襲名
1997年平成09年 宗完の名を兄の長男 分明斎にゆずり、宗心を名のる
卒寿記念に立礼卓を作る【兼中斎卒寿好松透:側面に松の透かし有】
堀内家の庵号(長生庵主)・斎号(兼中斎)著作に「茶の湯聚話(しゅうわ)」「茶花」など
【13代 宗完 斎号:分明斎】 11代 宗完幽峯斎の長男・兼中斎の甥
(当代分明斎も京都大学理学部卒)
1943年昭和18年生まれ
1997年平成09年 宗完を襲名 斎号:分明斎を名乗り当代13代となる
次代に紀彦氏がおられます。
【12代 宗完 兼中斎】
京都帝国大学理学部の出身で独特の茶風で知られる(当代分明斎も京都大学理学部卒)
1919年大正08年- 昭和後期-平成時代の茶道家【表千家流堀内家 12代 宗完(斎号(兼中斎)●隠居後(宗心))】
大正08年1月20日生まれ(名は吉彦)堀内家の庵号(長生庵主)
兄の11代が急逝したため,表千家13代千宗左に師事
1953年昭和28年 宗完を襲名
1997年平成09年 宗完の名を兄の長男 分明斎にゆずり、宗心を名のる
卒寿記念に立礼卓を作る【兼中斎卒寿好松透:側面に松の透かし有】
堀内家の庵号(長生庵主)●斎号(兼中斎)著作に「茶の湯聚話(しゅうわ)」「茶花」など
------------------------------
【影林宗篤(本名 清一)】
1946年昭和21年 奈良県生駒山に生まれる
1965年昭和40年 稼業の茶道竹工芸を学ぶ
1970年昭和45年 以降 三玄院 故、藤井誠堂老師や黄梅院の故、宮西玄性老師の指導を受ける